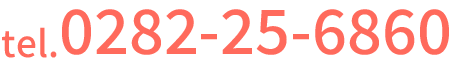妻に全財産を相続する内容の自筆証書遺言あったが、夫には前妻との間に子供がいた(栃木市都賀町)
依頼者はご主人を亡くされた奥様です。
お子様は長男と次男の二人です。
遺言が自宅の収納棚から見つかったので、当事務所に相談をしたいとのことでした。
依頼者宅にいくとチラシの裏面に「すべての財産は妻に相続させる」と手書きで書かれていました。全文手書き、日付、氏名、押印もされており、自筆証書遺言の様式は満たしていました。
ただ問題なのが、亡くなった旦那様は再婚で、先妻との間に2人の子供(長女、次女)がいました。
法的にはその2人も相続人なので連絡をする必要がありますが、依頼者(奥様)はその二人の連絡先も知らないし、面識もありませんでした。
当事務所の対応
このようなケースにおいて、自筆証書遺言が残されていたため、それを生かす方法を選択しました。全財産を依頼者様が相続することについては、実の子(長男・次男)は異論はありませんでした。問題は、所在も連絡先もわからない相続人2名(前妻の子供)です。
まず、当事務所で相続人調査を行いました。その結果この2人の生存の確認と所在地の特定ができました。
その後、お二人に宛てて、お父様が死亡されたのと遺言書が発見された件をお伝えしました。
お二人は共に50代で、遺言内容に問題はないとのことでご納得していただけました。
その後、自筆証書遺言を検認する申立(本人申立)を行いました。
手書きの遺言はそのままでは相続手続きに使えません。まず家裁に申し立てをして、指定日に相続人全員(原則)が集い、「本当に本人が書いたものかどうか」を確認する作業(検認)をする必要があります。
検認は必ずしも相続人全員が集らなくてはならないわけではなく、参加した相続人たちだけでこの手続きがなされます。上記2人は遺言内容は納得済みでしたのでお見えにはなりませんでした。
無事「検認」が済み、遺言内容に基づき相続手続きを完了させることができました。
結果
相続人への連絡、調整にくわえ、遺言書の検認があったため、通常の相続手続きより時間がかかりましたが無事完了し、依頼者様には本当に喜んでいただけました。今回のように自筆証書遺言があった場合で、現在の家族の他に相続人がいるケースだと手続きが複雑になります。おひとりで悩やまずに、是非相続の専門家に依頼されることをお勧めいたします。
業務実績エリア
栃木市、小山市、佐野市、下都賀郡、野木町、壬生町、足利市、宇都宮市、古河市、結城市、下館市、加須市、館林市、桐生市、太田市、邑楽郡、他
栃木県全域、茨城県全域、群馬県全域